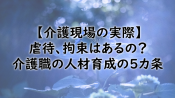介護離職防止!経験の振り返りで介護職を辞めさせない5つの鍵

みなさん、こんにちわ〜ケアびと育成コンサルタントのひらのまゆみです。
前回、離職に悩む介護職が持つネガティブな3Kな感情や、ボジティブな3Kな感情を元に、「意識変容」するヒントについて書きました。
今回は、経験学習という概念を知ることで、この状態から脱却できる鍵がきっと見つかります。
- なかなか、教えても覚えてくれない
- 何度も、同じ失敗を繰り返している
- 覚えるまでに、時間がかかる
- 指示を待って、自ら動けない
などの状態は、悩ましい課題です。
介護人材不足の中、新人教育やOJTにおいて、指導者や、熟達者が教える場面でのジレンマやストレスを感じることがあります。
職員の育成に悩む指導者や管理者の方は、一読ください。
介護職育成のための経験学習
介護職育成の場面で、育てやすい新人、育てにくい新人、あるいは育つスタッフと育たないスタッフがいます。これは素質や性格によるものなのか、経験の量や有無によるものでしょうか?
経験から学ぶことの重要性を指摘したのが、アメリカの哲学者・教育思想家であるジョン・デューイ(John Dewey)wikipediaです。
デューイは、学習者が環境に積極的に働きかけることで、学習者と環境の間の相互作用が経験となり、一つの経験が次なる経験につながるという経験の連続性の重要性を提唱しました。デューイの唱えた学習における経験の重要性は、企業内教育においても取り込まれ、「経験学習」と呼ばれる分野・領域を形成します。この経験学習は、現在、企業が人材育成・人材開発を進める際の中心的な理論になっています。企業が「経験学習」を展開する上で代表的な考え方とされるのが、デービッド・コルブ(David Kolb)による「経験学習モデル」です。
ボジティブな経験学習 とネガティブな経験学習
ボジティブな経験学習は、同じ失敗を繰り返しません。
ネガティブな経験学習は.何度も同じ失敗を繰り返します、落ち込み、自分を責めたり、他人のせいにしたりすることがあります。
具体的なこととしてこんなことがあります。
- 失敗から学んでいる
- ヒヤリハットを予見でき、事故を回避する力がある
- 全体や周りの状況をよく見ている
- 本質ついた発言ができる
- 改善アイデアを提案できる
- 冷静に、判断できる
- 粘り強く目標に向かう
- 何度も同じ失敗を繰り返している
- うまくいったことを、次に活かしきれない
- 言い訳や、愚痴が多い
- 過去の失敗をいつまでも気にしている
- 感情的な言動をしがちである
- すぐに諦め、継続できない
ネガティブな経験学習のパターンに傾くことや、抜け出せないでいるとしたら、経験学習モデルのサイクルを、行うことで、ポジティブな経験学習パターンにサイクルすることを行動を意識したいです。
介護職育成のための経験学習モデル
コルブのモデルは、①経験→②省察(振り返り)→③概念化→④実践という4つのサイクル・ステージで構成され、人はこれらを循環しながら学習していく。
学習とは知識を受動的に覚える事とその応用して、経験から持論、「マイセオリー」を作り出すことです。
体系化・汎用化された知識を受動的に習い覚える知識付与型の学習やトレーニングと区別し、「経験学習モデル理論」として提唱しています。
「経験学習モデル理論」
人は何から学び成長するのか(70・20・10の法則)米国のリーダーシップ研究の調査機関であるロミンガー社の調査によれば、経営幹部としてリーダーシップをうまく発揮できるようになった人たちに「どのような出来事が役立ったか」について聞くと、“70%が経験、20%が薫陶、10%が研修”という結果があります。
経験というのは「仕事」、薫陶というのは「上司の言葉」。これらに研修による「学びと気付き」を加えることで、実力・能力を今以上に持つことができます。
3−1 経験 Concrete Experienc
例えば、介護現場で、新人がベッドから車椅子に、利用者の方を移乗介助することを学ぶ時
といった介助場面で、たとえ介助手順書があり、業務マニュアルを読んだだけでは、新人スタッフはうまくできるようにはなりません。
必ず、育成者や先輩熟達者の職員は、眼の前で手本となる動作をやってもらい、新人スタッフも何度もやってみます。
しかし、新人スタッフは意識してみている所と、先輩熟達者は当たり前に出来てしまう動作は、注力するポイントが違っていることが多いです。
その違いを、先輩熟達者は自分がどこに意識して行なっているのかを、「見える化」することが求められます。
うまくいっている点を「この手の当てっている部分の力加減は良いが、重心をもっと低くして体重移動したほうがよい。」などと言ったような言葉にすることや、手本となる介助動作を繰り返し、繰り返し示すようにしないと、新人職員はうまくできません。
育成者や先輩熟達者は、自身の全身を使った動作・眼の動き・口の動き・音声などで、実際のどこに、どのようにして行なっているのかをありかかにすることが大切です。
3−2 省察 Reflective observation
経験を多様な観点から振り返ること。そのために必要な事は自分で自分に質問すること、振り返りを行うことです。私たちの脳は質問されると、それに答えようと働きます。質問には、自分の脳を活発に働かせる作用があります。
- 「どこに重心を置いて行なっているのか?」
- 「うまくいった時は、どんなことを考え、意識していたのか?」
- 「利用者の反応はどのような言葉を発して、表情はどうだったか?」など
また、多様な観点で、自分の行動を振り返ってみる。いつもと同じ視点、価値観で考えていたら、新しい「気づき」は生まれない。
いつもと同じ考えに陥り、いつもと同じ行動を繰り返すといったことがあります。
- 「具体的には、どういうことなのか」
- 「良い状態とは、どういう状態のことなのか」
- 「成功したことのイメージは。」
- 「うまくいった時とうまく行かなかった時との違いは?」
- 文字で書いて振り返る
- パソコンで打って振り返る
- 絵や図に書いて、目に見える所に張り出す
- 他人に話を聞いてもらいながら、振り返る
- 静かな場所で、一人で振り返る
自分の話した言葉や行動がより具体的に振り返りやすい自分のパターンを知って行なってみましょう。
3−3 概念化(持論化) Abstract Conceptualization
概念化とは、「本質的な要素を抽出すること」です。
概念化することは、次の望ましい行動につながることや、応用し自分の未来記憶が作れることや、他の人が使えるようにするためのものです。
3−4 実践(試行) Active Experimentation
新しい場面や、実際に試してみる持論(マイセオリー)を使う場面には「試行」の段階が必要です。本格導入は、その結果を踏まえて、100%でなくても使いながら、成長させていくことが大事です。
この場合、期間や変更条件、観察ポイントなどのルールをあらかじめ、合意しておくことをお勧めいたします。
介護職育成の省察的実践とは
学び方は、人それぞれです。必ずしも有効な学びや成長が生まれるとは限りません。
部下が成長の実感を持つことはあまり期待できません。大切なのは、自分の行動や仕事の成果について、自分で考えて自ら振り返る機会をいかに与えるかということです。省察的考察(リフレクション)と言います。
「省察的考察」や「抽象的・概念化」を自分一人で行うのは難しく、先輩熟達者の仕事ぶりを観察しながら、結果やプロセスを評価し、フィードバックしてくれる第三者の協力が必要なります。
「リフレクション」(reflection)とは日本語の「内省」の意味を持ちます。
人材育成におけるリフレクションとは、個人が日々の業務や現場からいったん離れて自分の積んだ経験を「振り返る」ことを指します。
起こった介護手技や仕事や業務の真意を探り、その経験における自分のあり方を見つめ直すことで、今後同じような状況に直面したときによりよく対処するための「智慧」を見出そうとする方法論です。
省察的実践から介護職育成できる5つの鍵
5―1 良質な経験の機会を持つ。
「予測し得ない結果をもたらす経験」のこと。
それは例えば、従来のスキルが通じない状況に直面したりすることで得られると考えられます。
そうした会に恵まれなくても、日常業務において、現在の能力の2割増しくらいの適度な難易度の課題にすすんで取り組んだり、懸命に手を伸ばせば届くような高さに成果の目標を設定したりすれば、成長につながる質のいい経験が期待できると思います。
5―2 自問自答や対話をしながら、内省する。
「なぜうまくいったのか」「なぜ失敗したのか」などを自らに深く問いかけることが求められます。
このような省察のプロセスを、業務の傍らで行うことは容易ではありません。
日常的な業務だけをこなす状態では、なかなか自分自身を客観的に振り返れません。
指導者や管理者は、本人の成長をサポートする他者の存在が重要になります。
1対1のコミュニケーションや面談をきめ細かく実施するなど、本人がメタな視点からの問いかけを受けられる環境を整備することが大切です。
YWT (Y:やったこと─W:わかったこと─T:つぎにやること)
YWTとは、個人やチームの「経験」「学び」を重視して振り返りを行う手法の一つです。経験学習の能力が高いとても有効な手法です。しかし仕事で経験を積もうとしない、起こった出来事を多様な視点で振り返ろうとしない、経験をほかでも応用できるように概念化しようとしない、新たな取り組みの際に試行・実践をしないなど、経験学習する能力が低い人だと効果が低くなりがちです。
指導者や育成者は部下が経験できやすい場を意識的につくること。対話のなかで本人の振り返りを促進させる働きかけが必要です。またYWTなどを活用しポジティブなフィードバックを実践することも良いでしょう。
5−3 より具体的な経験を主体的する。
指導者や育成者は、質問や対話から、新人自身の課題であることであり、課題を解決したいのか、望ましい未来を手に入れたいのかの確認をした上で、経験の機会を与えましょう。
具体的にかつ抽象的に自ら考えて、自ら動くことで、自身の結果を受け入れられるようになります。
さらに「気づき」が多くなるでしょう。
5−4 お手本者の考えや行動を真似る
自分の考えを照らし合わせましょう。まずは自分の状況と同じ状態の時のお手本者を真似ましょう。
さらに個別具体的に解釈し発展させ探すと、お手本者の智慧を見つけることができます。
5−5 マイセオリーを、試してみる
組織理論学者のミンツバーグ(H. Mintzberg)は、「すぐれた理論は、自分の経験を理解するのに役立つ」と述べています。
お手本者からの智慧や理論を、自分に置き換えて考えてみよう。自分の言葉にしてみよう。
マイルールや持論が生まれ、まずはうまくいく方法や感覚をつかみ、試してみることです。
そして、繰り返し、繰り返し経験学習のループそして振り返りながら進んでいく(省察的実践)の回転をさせることです。
納得した行動になり、自ら実践することになります。
まとめ
何か仕事をする上で、課題にぶち当たり、うまく進まないと感じた時、頭がごっちゃごちゃして、どうして良いのかわからなかった時、知識が不足していて行動できない時など、自分に質問し、文章にしたり、図にしてみたりすることで新たな気づきがあったりします。
また、他者と対話することで、学びや気づきがあったりします。
それはつまり、自分自身を洗練させることであり、悩みや迷いを克服していく作業であるとも思います。
まずは「課題に向き合い本質を探る」という姿勢が大切だと思います。
先輩熟達者やお手本からの学ぶことが、うまくいく成功への近道であります。
また自分のものにするためには、繰り返し、繰り返し行うこと、失敗経験を生かすことです。
小さく失敗経験を積み重ねるとの「気づき」が生まれ、成功体験につながります。
ここで重要なのは、小さい成功体験した自分を褒める、認めることです。
できればご褒美を自分に与える経験が、さらに望ましい未来につながることと信じてやみません。
それでは、最後まで購読くださいましてありがとうございます。