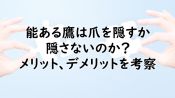【日本の贈り物文化】お土産、手土産、お中元、お歳暮は必要なの?

日本の職場では、休み明けや出張明けにお土産が配られることが多いけれど、それって必要なのだろうか?
長い休みの後など、どこにも行っていないのにわざわざ近所で手に入る菓子折りを持ってくる人までいることに驚いた。
お土産ってそんなに大事なのだろうか?
それとも日本人がお土産好きなだけなのだろうか?
日本人じゃないから、お土産は用意しなくてもいいのだろうか?
そんな迷いを感じている日本で働く外国人の皆さん、異文化通訳が得意なキャリアコンサルタントのMIYUKIが、約30年にわたり多国籍のビジネスパーソンと接してきた経験をもとにヒントを提供したいと思います。
日本の職場でみられる贈り物文化
まず、仕事がらみの贈り物にはどんなものがあるか、挙げてみましょう。
休みや出張明けのお土産、関係先訪問時の手土産、関係先へのお中元やお歳暮。
主に、これらの3種類に大別できるのではないでしょうか?
それぞれ品物を贈るという点では同じですが、少しずつ呼び名が違いますよね。
お土産は、旅先で買い求めたその土地にちなんだもの、手土産は、訪問先に持っていく挨拶代わりのお土産のことを指します。これに対して、お中元とお歳暮は、夏や年末という決まった季節にお世話になった方への感謝の気持ちを込めて贈るもので、少し性格が違います。
いずれも、消えてしまうもの、日持ちするもの、職場で配れるように個包装になったものが好まれます。
費用はというと、休みや出張明けのお土産は個人、お中元やお歳暮は会社が負担するのが普通です。関係先訪問時の手土産は、ケースバイケースですね。
では、それぞれの贈り物にどのような意味があるのか、順に確認していきましょう。
休み・出張明けのお土産
有給休暇であれ、出張であれ、あなたが職場を離れている間はあなたの仕事もストップ。そういう職場は今のところ日本ではあまりないのではないでしょうか。
用意周到な方なら、関係先に事前に休む期間を知らせておくことで、スケジュールのコントロールを図ることもできるでしょうけれど、担当者が不在であるという理由で放置できる仕事ばかりではありません。あなたの留守中は、同じ部署の上司や同僚が急な仕事や電話での問い合わせに対処してくれているというのが実情でしょう。
そんなのお互い様でしょう、と思うかもしれません。
そうですよね。それに、そもそも何事も起こらない可能性だってあるわけです。でも、自分の留守中に起こったことを情報共有してもらった経験はあるのではないでしょうか?
何らかの形で支えてもらっているという意識から、同僚へのねぎらいと感謝のしるしとして「留守中お世話になりました」という言葉とともにお土産を渡すのです。お土産は、職場の潤滑油のような役割も果たします。
確かに、お土産をもらって悪い気はしませんね。迷うくらいならお土産を配るというのは覚えておいてよい処世術と言えます。
さて、お土産は、消えてしまう食品などが普通とお伝えしましたが、職場を離れている間に経験した話もお土産になります!
仕事中におしゃべりするわけにはいきませんが、休憩時間などにおススメの情報を紹介すると良いでしょう。
また、お土産を渡すとき、どうしてそのお土産を選んだのか、母国からのお土産の場合にはその説明など、他愛のない話がコミュニケーションを深めるきっかけとして有効です。
関係先訪問時の手土産
ビジネスの目的で関係先を訪問する時には、何も持たずに訪問する場合が多いのは事実です。でも、時によって手土産を持参して訪問する場合もあります。
たとえば、初めて訪問するとき。ご挨拶を兼ねて手土産を持参することがあります。
お土産などなくても良いのですが、時間を割いてもらうことへの感謝、今後のお付き合いのお願い、そして何よりもその場が和むので持っていくのです。
既存の関係先を訪問する場合に手土産を持っていくのは、お詫びをする場合を除けば、訪問者の機転によることがほとんどです。
それまでの会話から相手の好みを知っている場合、珍しいものが手に入った場合など、ビジネスの成否よりも人間関係に重きをおいて持っていきます。広い意味での仕事‘仲間’への配慮を示すことは、関係構築に役立つだけでなく、仕事に活かせる情報収集・交換につながることもあります。
つまり、個人に贈るというよりも、職場の皆さんでどうぞという意味で渡します。
お中元・お歳暮
既に取引のある相手先に対して、日ごろの感謝を示すために夏と年末の決まった時期に贈り物をする習慣があります。
年末は、日ごろの感謝に加えて「翌年もよろしくお願いします」という気持ちも含めます。夏(関東では7月上旬から15日))をお中元、年末(11月下旬~12月20日)をお歳暮と呼びます。
「職場の皆さんでどうぞ」という点は手土産と同じですが、昨今では持参するよりもデパートなどから送るのが主流です。
交際費として計上するものですが、投資的な意味合いがあります。
投資効果を上げるには、形式的に贈るのでなく、気持ちを込めること、すなわち研究も大事です。特にこの時期は他社と比較される可能性も多分にありますので、普段から相手先の職場を観察したり、世間話を通じて情報を集めておくことが品物選びに役立ちます。
ところで、ビジネスでお中元やお歳暮を贈る際には気を付けておくポイントが5つあります。
- お中元を贈ったらお歳暮も贈る
- 年に一度だけ送るならお歳暮
- 一度きりなら御礼として贈る
- 贈答禁止の企業もあるので、事前に確認する(担当者に迷惑をかけることになります)
- 相手が公務員の場合は、倫理規定違反に当たる場合があるので要注意
マナーを守って関係先との関係構築に活用しましょう。
以上、日本の職場における贈り物文化について、その意味合いについてお伝えしてきました。そのなかで、贈り物は感謝の気持ちを表すための手っ取り早い方法のひとつであるということを理解していただけたと思います。
日本人はお土産が好き?
ところで、海外の人、特に欧米の方には日本人はお土産好きだと映っているようです。
日本人が旅行先で同じものをいくつも、親戚や友人、会社の同僚用にと買い求めている姿がそのように見えるのでしょう。実際に、観光に来たはずなのにお土産調達で疲れてしまうということも自分の経験では多々あります。
一方、欧米の人と旅行しても、会社の同僚にお土産をたくさん買うという印象はありません。むしろその五感でその場を楽しむことに集中しているように思います。
お土産屋さんには関心を持って入りますが、たいていの場合、眺めるだけで満足している様子。せいぜい旅の記念にと自分のために何かを買うくらいですよね。
また、前の職場で海外から客人を迎えたときについて思い出してみると、お土産の代わりに、「お薦めのお店でごちそうさせて」とか「一杯おごるよ」ということがありました。それが私にはとても新鮮に感じられました。感謝の気持ちを示すのに、必ずしも母国ゆかりの品である必要はない、現地調達でも良いという考えなのですね。
仕事がらみの場面では、日本人はお土産が好きというよりも、お土産を買わなければという使命感が強く働いているように思います。

豆知識:つまらないもの
ところで、誰かに贈り物を渡すとき、日本人が「つまらないものですが」と言うのを聞いて、おかしなことを言うのだなと思った経験はありませんか? つまらないものを他人にあげるなんてありえない、と思う人もいますよね。
もともとは、「贈り物を渡す相手と比較すると、見劣りしてしまうものですが」という謙遜して使う言葉なのです。
英語ならnothing special とかlittle somethingが近いので、「ちっちゃいものですが」と言って大きな額絵をくれた外国人がいました。「つまらない」に抵抗があって考えたのかもしれません。
日本人がそう言うからといって、真似なくても大丈夫。「気に入っていただけると良いのですが」で問題ありません。それはつまり、「あなたに相応しいものを精一杯選んだつもりです」という意味でもあります。納得したフレーズだけ覚えてくださいね。
まとめ
日本の贈り物文化について、職場がらみの習慣についてお伝えしました。お土産、手土産、季節の贈り物(お中元・お歳暮)は、いずれも感謝の気持ちを伝える手段として有効です。
外国人の皆さんが戸惑う職場へのお土産については、コミュニケーションを深め、文化交流を図るツールとしての役割という意味で、あると効果的とお伝えしました。
ただし、お土産を配ればよいという意味ではありません。
気持ちが伴わなければ意味がありません。
お土産が用意できなくても、「留守中ありがとうございました」という感謝の言葉をかけることは忘れないようにしましょう。