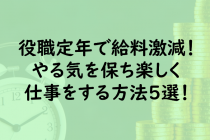【50代】役職定年から準備するセカンドキャリア!長く働き続ける秘訣は独立起業

55歳で役職定年なったけど、65歳まで雇用延長もあるので、安泰と思っていたビジネスパーソン。
しかし、新型コロナでの会社の業績不振が起こり、あっという間にリストラ(退職勧奨)対象者。
あげくに、何の準備もできないまま転職市場に投げ出され、ハローワークに通い続けるも面接にすら至らず、途方に暮れている話を最近よく聞きます。
一方社会は、少子高齢化が進む中において、生産人口を増やすため、高齢者に長く働き続けることを期待しています。
ただ、長く働きたいと思っても「定年60歳」「再雇用延長65歳」と国や会社が決めた区切りがあるので、雇用される働き方では限界があります。
それではどうしたらいいのでしょうか。
これからは、長年培ってきた知識・スキル・ノウハウを生かして、こずかい稼ぎではなくて実際に生活をささえることができる収入を年齢に関係なく獲得できる働き方を目指す必要があるのではないでしょうか。
その働き方とは、独立起業の一つでもあります「独立業務請負人(雇用契約ではなく、業務委託契約を複数の会社と結んで活動する)」だと思っています。
そして、中高年のセカンドキャリアは、「優秀であったかどうか」ではなく、「事前にどれだけ準備したか」によってきまります。
そのために、役職定年という一つの節目を迎えたころから、考え、準備し始める必要があるのです。
中高年危機脱出キャリアコンサルタントの坪根克朗が、「独立業務請負人」になるための準備や行動についてお話していきます。
中高年を取り巻く環境
70歳まで働ける法改正
2021年4月から施行される「改正高齢者雇用安定法」では、65歳までの雇用確保は義務になり、そのうえで70歳までの就業確保の努力を会社に課します。
その努力とは、「70歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」といったほかに「65歳以上については、雇用にこだわらず会社が従業員の独立を支援すること」を施策として盛り込んでいます。
このことから、国も会社も本音として、65歳以降は自分で稼いでほしいと言っています。
テレワークの進展
新型コロナの影響にともなってほとんどの会社でテレワークが導入されています。
テレワークとは「tele=離れた所」と「work=働く」をあわせた造語で、ICTを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を意味します。
そして、このテレワークは、雇用されないフリーランス的な働き方を実現する追い風になっているのです。
コロナで中高年のリストラの加速
新型コロナで着々と進んでいるのが、中高年へのリストラです。
もちろん解雇といった過激な形で行われることはほとんどありません。
「早期退職・希望退職優遇制度の募集者を募る」といったソフトな形で行われます。
早期退職優遇制度とは会社があらかじめ退職における有利な条件(退職金の加算等)を示すことにより、会社に雇われている社員が自らの意思でこれに応じ、労働契約の解除をすることです。
各社が希望退職を募集する時の共通する条件、それは、募集者対象者の条件を「45歳以上」すなわち中高年を意味しています。
会社が社員を「居る・要らない」の判断するのがこの年齢なのです。
定年(60歳)で辞めると年金をもらうまでが長い
現在、公的年金の支給開始年齢は、原則満65歳からです。
そのため「昭和36年4月2日以降に生まれた男性」「昭和41年4月2日以降に生まれた女性」は、全員65歳からの支給となっています。
したがって、定年(60歳)で辞めてしまうと、公的年金をもらうまで5年くらいは無給になってしまう可能性があります。
中高年の定年後のセカンドキャリアの選択肢
中高年が考える定年後のセカンドキャリアの選択肢には、「定年後再雇用」「転職」「独立起業」があります。それぞれの選択肢について考えてみたいと思います。
定年後再雇用
リスクは一番低い
給与は半減しますが、長年慣れ親しんだ会社で再雇用されることは、あなたにとって、短期的には一番リスクの少ない選択になります。
定年後再雇用は非正規雇用と同じ
定年後再雇用は、「1年ごとに契約更新を行う非正規の有期契約社員」ということになります。
したがって、定年後再雇用を選択する場合は、労働条件(賃金・賞与、休暇、休職制度、福利厚生制度)が正社員の時と比べてどのように変わるか調べたうえで選択する必要があります。
再雇用の仕事が気に入らない可能性もある
再雇用の場合、会社は、賃金を減らすのですから賃金に見合った仕事にしなければいけません。
定年前と同じ仕事をして、同じ労働条件で働いているのに、賃金だけ下げると法律違反になります。
そして、再雇用の進め方もいろいろあります。
例えば、会社側から業務内容のオフアーがあって、それを「受けるか・受けないか」の選択、または、社内応募を出して希望者を募るという方法になります。
再雇用できたとしても、「自分の希望するやりがいのある仕事になる」とは限らないことは知っておいたほうがいいでしょう。
転職
中高年(50代)の転職は四捨五入
50代からの転職には、「四捨五入の法則」があると一般に言われています。
54歳まではなんとかなるが(賃金ダウンは織り込み済み)、55歳を超えると職を得ることすら難しいという説です。
会社は採用にあたって、短期間で目に見える成果を期待しています。
次に、3年あるいは5年を一区切りとした中期経営計画レベルで成果をだしてもらうことを期待します。
これが、55歳以降の転職では1回廻して定年になってしまいます。
それが、55歳を超えると転職が難しい理由になっています。
部長職が一番転職できない
今の時代、職位が高ければ高いほどキャリアに関するリスクは高いのです。
以前は、部長まで登りつめれば、大企業であれば子会社の役員などへの天下りが可能でした。
しかし、今は、子会社も付加価値を生まない管理しかできない部長を受け入れる余裕はありません。
また、実際のライン実務の第一線から離れて久しい社内調整を中心にしてきた管理職も市場からもとめられていません。
中高年からの独立起業
中高年からの独立起業は案外考えやすいものです。
中高年が独立起業を考えやすい理由

中高年の独立起業のリスク
中高年の独立起業には、中高年以外の独立起業とあまりかわりはないですね。

長く働き続けるセカンドキャリアとは
中高年にとって働き続けるためにセカンドキャリアをどのように考えていけばいいのでしょうか
セカンドキャリアの準備を始めるタイミングは役職定年
役職定年は、会社からの戦力外通告
役職定年については、私のブログで書いたように「役職者が一定年齢に達したら管理職ポストをはずれ、専門職などに異動する制度」で人事の新陳代謝を促し、組織の活性化を図ることを目的としています。
いうなれば役職定年になった社員は、会社から「戦略外通告」を受けたみたいなものです。
戦力外通告を受けた時こそ、一度たちどまって自分のキャリアを考える
今50代の皆さんは、会社人生に疑問と不安を抱きつつも、ひたすら会社のためにお役に立ちたい、貢献したいと思ってひたすら頑張ってこられたと思います。
会社から戦略外通告を受けた今こそ、自分のキャリアについて真正面から考えはじめ、きちんと気持ちを整理したうえで、自分自身のセカンドプランを考えはじめ、準備をしていけばいいのではないでしょうか。
経験・スキルの商品化が中高年のセカンドキャリアの鍵
会社人生での何十年の経験・スキルが商品化できれば中高年のセカンドキャリアは成功したも同然になります。
中高年のお勧めは「独立起業」
中高年のセカンドキャリアの選択肢そして考え方をみてきました。
その結果、「再雇用」「転職」にしても雇用される働き方は、必ず区切りがあるので、長く働き続けるためには、「独立起業」が一番だと思っています。
ただ、会社をつくって「新しいイノベーションを起すビジネス」を立ち上げろとは言っていません。
中高年がスモールスタートを切りやすい「独立業務請負人(インディペンデントコントラクター)」という働き方をお勧めします。
独立業務請負人とは
会社と、雇用契約ではなく、業務単位の請負契約を結び、期限付きで専門性の高い仕事を行う個人事業主のことを言います。
豊かな実務経験、高度の専門知識、すぐれた技能をもち、会社と対等の立場で契約を結んでいるので、会社からの指揮系統から独立していて勤務時間などにも自由度が高く、複数の会社と契約して活動することもできるものです。
人事、経理、総務、採用サポート、セミナー講師、ITのプロジェクト管理、経営コンサルタント等など多方面にわたって活躍できます。
欧米では「ギグワーカー」という名称で定着し、普及しています。
私は、終身雇用崩壊後の新しい働き方として「ギグワーカー」についてブログで紹介しています。
独立業務請負人として成功する方法
現役時代から個人事業主マインドをもって仕事をする
個人事業主マインドとは、会社ではなく「仕事へのエンゲージメント」をもつことになります。
中高年にとってのエンゲージメンとは一般的には「会社への満足度が高く愛着をもっているといった忠誠心的な意味あい」で使われることが多いです。
しかし、中高年、特に役職定年になってからは、仕事エンゲージメント(仕事に対する熱意があり、モチベーションが高い)に注力する必要があります。
中高年一人ひとりが、会社・組織の指示に従うのではなく「自発的に自分の力で仕事を進めていく」という自律した意欲をもつことが重要になってきます。
自分の「売り」なる商品(サービス)を作る
独立業務請負人になるのは、キャリアの棚卸を通して、「自分の得意な領域」「会社に貢献できた工夫点やノウハウ」を思いだすことによって、自分の「売り」になる商品(サービス)を見つけることが必要になってきます。
「自分な得意な領域」を見つける
キャリアの棚卸とは、「これまで携わってきたすべての仕事について書き出し、整理すること」です。そして、キャリアの棚卸のアウトプットが職務経歴書になります。
私の行っている「職務経歴書作成支援」では、職務経歴書の中に「アッピール実績」を下図のような感じで「STARS」の法則に従って書いてもらっています。
このアッピール実績こそ、「自分の得意な領域」になり、本人も書いてみて初めて気が付くこともあります。
また、アピール実績を書くことによって、「過去の実績の再現性」「新しい会社・仕事への貢献の可能性」をお客さんに読み取ってもらうことができます。

得意領域に「タイトル」をつける
自分の得意領域が見つかったら、それに「タイトル」をつけるのです。
得意領域は、あなたが長年培ってきた固有・独自の一品一様の専門領域でもあります。
それを、例えば「給与計算全般」「人事」「経理」「営業」といった大きな括りの中で埋没させるのは、もったいないです。
そのため、給与計算担当シニアは、「給与システム導入コンサルタント」「年末調整アドバイザー」「税務調査対応スペシャリスト」といった具合に職種や職務は「〇〇スペシャリスト」の自分でタイトルを作ってしまえばいいのです。
私も中高年専門のキャリアコンサタントですが、それだけではインパクトが弱いと思い、現在は、中高年の方々が抱えるいろいろな危機を乗り越える支援する専門家として「中高年危機脱出キャリアコンサルタント」というタイトルをつけた名刺を作り配っています。
得意領域を「アウトプット」する方法
次は、得意領域をアウトプットする方法についてお話します。
得意領域をアウトプットするのは、自分の得意領域の「パンフレット」を作る感じになります。
昔、フォルダー型で1枚1枚リーフレットを差し込むタイプの商品紹介パンフレットを見たことありませんか。
この要領で、自分の得意領域での商品(サービス)をアッピールするのです。
具体的には、商品(サービス)は、職務経歴書で書いた「アッピール実績」の中の「Action(何を実行したのか)」そのものになります。
そして、「商品(サービス)内容」「特徴」「お客さまにとってメリット」「提供価格」を1件1様として、リーフレット(A41枚)にまとめるのです。
担当したプロジェクトや職歴は多岐にわたるでしょうから、5~6枚は作れると思います。
これで、あなたがお客さんに提案できる商品(サービス)は、5~6件できあがります。
今の会社を業務請負人の最初のクラインアントにする
業務請負人として、最初のクライアントは今の会社がベストです。
会社との信頼関係があれば、WinWinの関係が作りやすいのでスタートアップには最適です。
今やっている現業業務を継続することが基本
今、会社と雇用契約を結んでいる仕事を、退職後は業務請負人として「業務委託契約」を結んでもらえばいいのです。
価格交渉は、再雇用延長時の給与から始める
定年再雇用延長後などに予定される給与水準を基本委託料のベースとして会社と話しを始めればいいと思います。
会社として想定していた給与水準なので合理性もあり、現場だけでなく、社内の同意も得やすいです。
業務委託契約は、会社側の費用的メリットも多い
社員として働いてもらうより、業務委託契約をすることは会社にとっても費用的メリットも多いです。
一般的に社員として働いてもらうと、社会保険・労働保険の会社負担分や福利厚生費、臨時給与(賞与)を含めると額面給与の1.4倍の費用負担をしています。
それがなくなると、会社として費用的メリットは大きいです。
今の会社で業務請負人になるための留意事項
フルタイムはやめる
業務請負人のメリットは、複数の会社と取引できることですから、勤務はフルタイムで働くのではなく、週3~4日にしてもらうといいと思います。
現業業務のほか付加価値もつける
今の会社と業務委託契約を満足してもらい、信頼関係を深めるためにも、現行業務に加えて、「あなたがもつノウハウの形式知化(注1)」「若手指導行う」等付加価値をつけてあげれば、会社から感謝され、高い費用での契約を勝ち取ることができるかもしれません。
まとめ
中高年の皆さんは日本企業の終身雇用制という働き方の中で、長い時間をかけて、原理・原則に基づいた奥深いノウハウや知識を蓄積し、濃厚な人脈ネットワークを形成されてきました。
このスキル人脈は貴重であり、それを生かさない手はないと思っています。
幸いにして、テレワークやインターネットのIT技術の進展によって、雇用に限らず、多様な働き方が実現できる環境が整いつつあります。
今回紹介した「業務請負人」としての働き方は、中高年の方々にといって、最も最適な働き方だと思っています。
ただ、業務請負人になるにあたっての肝である「自分の売りになる商品(サービス)」を作ることが苦手な人が多いのも現実です。
私は提供している「中高年危機脱出相談サービス」では、面談を通して「あなたの売りになる商品(サービス)」をいっしょに作ることができます。